大腸癌やその他大腸の疾患に対して行われる大腸切除ですが、病変の位置によってガラッと手術の内容が変わりますし、起きやすい合併症にも違いがあります。
- 大腸の切除範囲について
- 合併症について
- 人工肛門について
大腸の切除範囲について
大腸は人間のおなかの中を右下から、「上行結腸→横行結腸→下行結腸→S状結腸→直腸→肛門」という順に「?」の形のように走行しています。
大腸切除と一言で表現しても、病変の位置によって切除する範囲が変わり、手術内容もガラッと異なってきます。
①結腸部分切除術、②回盲部切除術、③結腸右半切除術、④結腸左半切除術、⑤S状結腸切除術、⑥直腸切除術、⑦直腸切断術など、大まかに分けてもこれだけあります。
①結腸部分切除術
癌などの悪性疾患では、病変+α(病変の端から数cm~10cm程度の腸管、リンパ節郭清)をすることが多く、癌の位置する部位に応じて切除する血管、切除範囲が基本的に決まっています。
悪性疾患でない場合、病変部位を切除するだけでよいので、+αの部分がなくなり、部分的に大腸を切除すればよいことになります。
②回盲部切除術
回盲部切除術は回結腸動脈を切離する術式で、癌などの病変が大腸が始まってすぐのところに位置していた場合、小腸の一部と大腸の一部を切除し、小腸と上行結腸を吻合する術式をいいます。
③結腸右半切除術
結腸右半切除術は回結腸動脈と中結腸動脈右枝を切離する術式で、回盲部切除術と手術の内容としては似ていますが、回盲部切除術は大腸を上行結腸で切離するのに対して、結腸右半切除術は横行結腸で切離します。
吻合は回盲部切除と同様に小腸と大腸を吻合します。
④結腸左半切除術
結腸左半切除術は中結腸動脈左枝と左結腸動脈を切離する術式で、横行結腸とS状結腸を切離し吻合する術式です。
⑤S状結腸切除術
S状結腸切除術はS状結腸動脈を切離する(もしくは下腸間膜動脈根部で切離する)術式で、下行結腸と直腸を切離し吻合する術式です。
⑥直腸切除術
直腸切除術は上直腸動脈と中直腸動脈を切離する術式で、S状結腸と直腸を切離し吻合する術式です。
⑦直腸切断術
直腸切断術は、⑥の直腸切除術と切離する血管や口側腸管はほとんど同じですが、病変が肛門に非常に近く、肛門側腸管が残せない場合に選択される術式です。
「切離」ではなく「切断」になるので、肛門側の腸管を切離するのではなく肛門をくりぬいてしまいます。
つまり、この術式においては人工肛門は必須であり、永久に人工肛門と付き合っていくことになります。
合併症について
大腸の手術において起こりうる合併症について、ほんの一部紹介していきます。
- 出血
- 縫合不全
- 腸閉塞
- 排尿障害、排便障害、性機能障害
①出血
どんな手術においても出血をゼロにすることはできませんが、大腸の手術においては、出血しやすい部位があり、そこには注意して手術する必要があります。
回盲部切除術、結腸右半切除術において、胃結腸静脈幹に流入する副右結腸静脈は、術式上絶対に切離しないといけない血管ではないですが、腹腔鏡での腹腔内操作を終了して体外操作に移行する際、動脈よりも弾力がなく切れやすい静脈のため、腹腔内で出血をきたしていることがあります。
体外操作で吻合が終了して、「ふー。今日の手術も無事に終わったなー。」なんて思って、腹腔内を再度観察しにいくと血の海、、、なんてことがあります。
腸間膜の脂肪が多く、体外操作の時に血管にテンションがかからないような状態でなければ予防的に切離しておく方がよいと思います。
このような予期せぬ出血の場合、輸血や血液製剤を手術中に使用することがあるため、そういった製剤を使いたくない人は先に主治医の先生に申し出ておくとよいと思います。
②縫合不全
外科医が一番嫌う合併症といっても過言ではないです。縫合不全は文字通り、腸と腸のつないだ箇所から漏れてくることをいいます。
これはどれだけきれいに手術ができても一定の確率でおきてしまうものです。
縫合不全が起きた場合、漏れた便が一部にとどまって膿瘍形成にとどまれば、絶食+ドレナージで自然に穴がふさがることもあります。
ただ、漏れたものが腹部全体に広がり、汎発性腹膜炎という状態になると緊急手術が必要になり、吻合部よりも口側の腸管(大腸もしくは小腸)で人工肛門を造設し、吻合部が固まった時点で人工肛門をなくすという二期的な手術が必要になることもあります。
③腸閉塞
大腸の手術に限らず、胃や腎臓、大動脈、帝王切開などの腹部の手術では共通して起こりうる合併症ですが、腸閉塞というものがあります。
腹腔内の手術をした部位や吻合部、おなかの傷が治る段階で、小腸が巻き込まれて治ったり、ひっついたまま固まってしまった場合、その部分の小腸で狭窄を起こして腸の通過障害を起こすことがあります。
しばらく絶飲食で休めていればよくなるような腸閉塞もありますが、閉塞症状を何度も繰り返したり、2か所以上の狭窄によって閉鎖的な空間ができてしまい、腸管内の圧が抜けない状態(closed loop)になってしまうと手術で癒着剥離が必要になったり、場合によっては腸切除が必要になることもあります。
④排尿障害、排便障害、性機能障害
これらは合併症というよりは、手術後の後遺症といった方がいいかもしれません。
S状結腸切除術や直腸切除術/切断術の場合、直腸の背側の剥離が必要になりますが、そこには腰内蔵神経や上下腹神経、左右下腹神経、骨盤内蔵神経など様々な神経が張り巡らされています。
基本的には最小限の切離で済むように、神経は傷つけないように手術をしますが、病変が神経に浸潤していたりしてやむを得ず神経を切除しないといけないこともあります。
それらの神経は、排尿や排便、勃起や射精を司っている神経のため、神経を損傷や切除すると術後にそういった機能に支障をきたすことがあります。
排尿障害の場合、薬剤や日にち薬で改善することもありますが、しばらく自分で排尿できなくなるため自分で尿道にチューブを入れて排尿する自己導尿が必要になることもあります。
排便障害の場合、便意を催す頻度が高くなったり、便失禁するようになったり、逆に便秘になることもありますが、こちらも術後しばらくすると症状が落ち着くことが多いです。
人工肛門について
最後に人工肛門について一言入れておきます。
上記の通り、直腸切断術においては本来の肛門がなくなるため人工肛門が必須ですが、その他の手術においては人工肛門は必須ではありません。
では、どういったときに人工肛門を作ることになるのかというと、僕が考える人工肛門の立ち位置は、「縫合不全が起きた時、縫合不全が起きそうな時に作る応急処置」というイメージです。
最初から人工肛門ありきの手術は少ないですが、吻合部が肛門に近ければ近い程縫合不全は起きやすく、併存疾患が多く組織が弱い人では縫合不全は起きやすいです。
縫合不全が起きてから人工肛門を作ったのでは後手に回ることになり、全身状態が悪くなってしまうことが予想されます。
また、併存疾患や年齢によっては、縫合不全によって汎発性腹膜炎になってしまうと救命が困難になる可能性が高い人もいます。
その場合、「縫合不全になるかならないかわからないけど、なったら一大事だからひとまず人工肛門を作って縫合不全は免れよう。数か月吻合部の漏れがないことがわかったら人工肛門をなくそう。」という流れで人工肛門が選択されることがあります。
人工肛門を作られた方が自宅でどういった生活をしているか、どれほどのストレスを抱え、生活にどういった弊害があるのか、100%理解でいている外科医はほとんどいないと思います。
できることなら人工肛門なく自宅に退院させてあげたいですが、救命優先の状況ではそうも言ってられないこともあります。
病院によっては、WOCナースといって日本看護協会が認定する皮膚・排泄ケア認定看護師がいる場合がありますので、人工肛門に関して困ったときには相談窓口になってくれることが多いです。

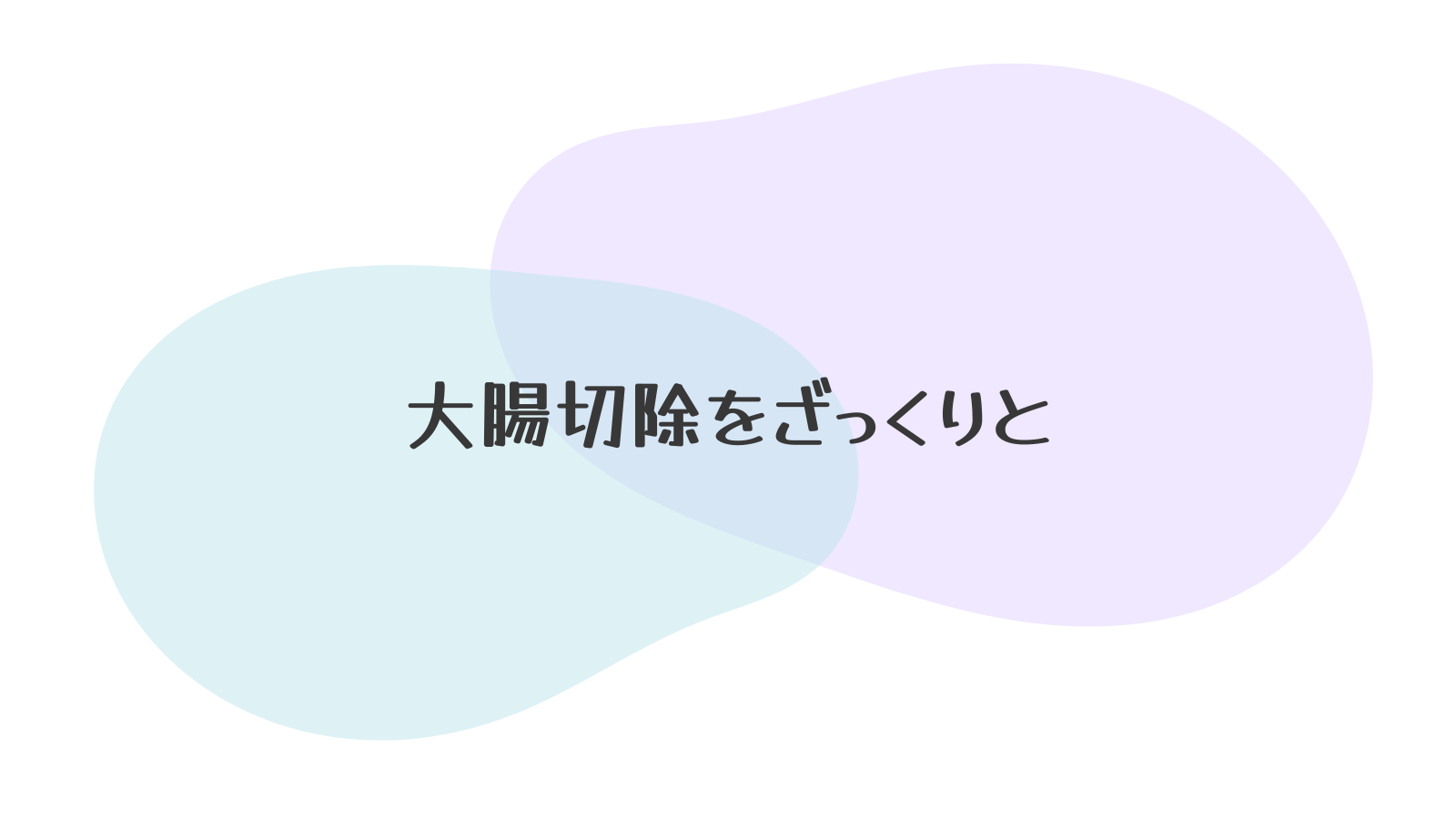

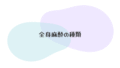
コメント