今日は鎮痛薬について学んでいこうと思います!
・レミフェンタニル
・フェンタニル
・モルヒネ
・アセトアミノフェン
・NSAIDs
私自身、周術期に使用することの多い鎮痛薬はこれくらいでしょうか。
今回は全身麻酔で使用する鎮痛薬と術後鎮痛について書いていくので、
局所麻酔薬については別の記事で書こうと思います。
各鎮痛薬の特徴と使い方
レミフェンタニル
作用持続時間が3~10分と超短時間作用型
全身麻酔の導入、維持に使用
術後鎮痛には使用できない。
■全身麻酔の導入
気管挿管時 0.5~1.0㎍/kg/min
1.0㎍/kgを単回投与することもあり
■全身麻酔の維持
0.25㎍/kg/min (0.05~0.5㎍/kg/min ※2.0㎍/kg/minを超えない)
■硬膜外投与
なし
■くも膜下投与
なし
■注意点
徐脈
低血圧
呼吸抑制
筋硬直
術後に向けて他の鎮痛薬を併用する必要あり(tranditional analgesia)
フェンタニル
作用持続時間が30~60分とレミフェンタニルより長い
全身麻酔の導入・維持、術後鎮痛に使用される
循環動態への影響が少ない
■全身麻酔の導入
1.5~8.0㎍/kgを緩徐に静注
■全身麻酔の維持
間欠投与 25~50㎍ずつ静注
持続投与 0.5~5.0㎍/kg/hr
■術後鎮痛
1.0~2.0㎍を緩徐に静注後、1.0~2.0㎍/kg/hrで点滴静注
■硬膜外投与
▼術中
単回投与 25~100㎍
持続投与 25~100㎍/hr(0.5~1.0㎍/kg/hr程度)
▼術後
単回投与 4~50㎍
持続投与 4~30㎍/hr
■くも膜下投与
鎮痛効果の増強や鎮痛範囲の拡大効果として使用
5~25㎍を単回投与
■注意点
呼吸抑制
気道閉塞
硬膜外、クモ膜下投与の際は局所麻酔薬などと併用
モルヒネ
作用持続時間が2~4時間と長時間作用型
全身麻酔中に使用されることは少ない
術後鎮痛として使用することが多い
■皮下注or静注
皮下注 5~10mg/回
静注 5~200mgを静注
■硬膜外投与
静注よりも少量で同等の鎮痛効果が長時間得られる
単回投与 2~6mg/回
持続投与 2~10mg/日
■くも膜下投与
硬膜外投与よりも少量で鎮痛効果が得られる
0.1~0.2mg(最大0.5mg)を単回投与
■注意点
遅発性呼吸抑制
▼硬膜外投与時の危険因子
・単回投与(4mg以上)
・繰り返し投与(2mgを12.5時間以内に2回以上)
・他のオピオイドや鎮痛薬の全身投与
・高齢者
・偶発的なくも膜下投与
アセトアミノフェン
抗炎症作用はほとんどない
新生児期から使用可能
■術後鎮痛
▼アセリオ
成人 300~1000mg/回を15分かけて静注(50kg未満は15mg/kg/回を上限)
2歳以上 10~15mg/kg/回を15分かけて静注
2歳未満 7.5mg/kg/回を15分かけて静注
■注意点
過剰投与による肝障害
NSAIDs
抗炎症作用あり
内服、坐薬、静注薬など多数あり
■術後鎮痛
▼ロピオン
50mg/回をゆっくり静注
▼ジクロフェナク坐薬(ボルタレンサポ)
成人 25~50mg/回を挿肛
小児 0.5~1.0mg/kg/回を挿肛
■注意点
消化性潰瘍には禁忌
妊娠後期には禁忌
ウイルス感染症、血小板低下、喘息に注意
乳児には原則使わない
拮抗薬(ナロキソン)について
オピオイドの過量投与による呼吸抑制など
副作用が強い場合に用いて作用を拮抗することができる
いずれのオピオイド受容体にも拮抗作用を持つ
■投与方法
▼添付文書
0.2mgを静注
効果不十分の場合、さらに2~3分間隔で0.2mgを1~2回追加投与
▼麻酔科学会
0.04~0.08mgを静注(10倍希釈して使用)
持続静注 2~10㎍/kg/hr
■注意点
・オピオイドよりも効果持続時間が短いので、
反復投与や持続投与が必要になる可能性あり
・呼吸抑制のみを拮抗したいが、
ナロキソンの投与量が多いと鎮痛作用まで拮抗してしまう
→ 10倍希釈にして1~2mlずつ投与する方法で緩和できる
PCAについて
術後の鎮痛薬の管理方法に、
患者自己調節鎮痛法(patient-controlled analgesia:PCA)という方法があります。
痛みの感受性には個人差があるため、
術後鎮痛薬を一定量投与しても
その患者個人に適切な量とは限りません。
そこで、鎮痛薬を持続投与はしつつも、
患者自身が痛みを自覚したときに手元に準備されたボタンを押すことで
自動的に鎮痛薬を追加投与できるようにしたポンプを利用して
術後疼痛を管理するのがPCAです。
追加投与後は、
ボタンを再度押しても一定時間内では追加投与できない設定になっており、
投与量も医療者側で設定してあるので、
患者自身での過剰投与は防止されています。
患者自身が自分で疼痛コントロールすることで
疼痛に対して迅速に対応でき、
患者本人の精神的安心にもつながると考えられています。
PCAの投与経路には、
主に静脈と硬膜外の2種類あります。
IV-PCA(静脈)
内服薬や患者要因によって
硬膜外カテーテルが留置できない場合に選択されることが多い。
硬膜外鎮痛に比べると
体動時痛や創部処置の疼痛には効きにくい。
例)フェンタニル
・濃度 20㎍/ml
・持続投与量 20~50㎍/hr
・1回投与量 10~50㎍
・ロックアウト時間 5~10分
PCEA(硬膜外)
局所麻酔薬にオピオイドを混入させることもあり。
持続投与のみでは徐々に神経遮断領域が狭くなるため、
持続投与にボーラス投与を加えることで適切な遮断領域を維持できる。
そうすることで局所麻酔薬やオピオイドの使用量を減らし、
悪心嘔吐などのオピオイドの副作用や
局所麻酔薬による運動麻痺を減らすことができる。
例)0.2%ロピバカイン±フェンタニル
・組成(合計200ml)
0.2%ロピバカイン 200~184ml ± フェンタニル 0~800㎍
・持続投与量 2~6ml/hr
・1回投与量 3ml
・ロックアウト時間 30分
まとめ
以上、今回は、
術中に使用することが多いオピオイドと拮抗薬のナロキソン
術後鎮痛に使用する鎮痛薬
術後鎮痛のPCA
について簡単にまとめてみました。
私自身、
「この薬ってどれくらいの濃度と速度で投与するんだっけ?」
とわからなくなることも多いです。
だんだんと慣れてきたら、
自分なりのレシピや方法ができてくるのだと思いますが、
今は必要な時にさっと調べられるようにしたいので、
私自身の確認のためにも記事を残しました。
各病院や指導医の先生によって
使い方や考え方は違うと思うので、
あくまで参考にする程度で見ていただけたらと思います!
次回は局所麻酔について学んでいこうと思います♪
ではでは~

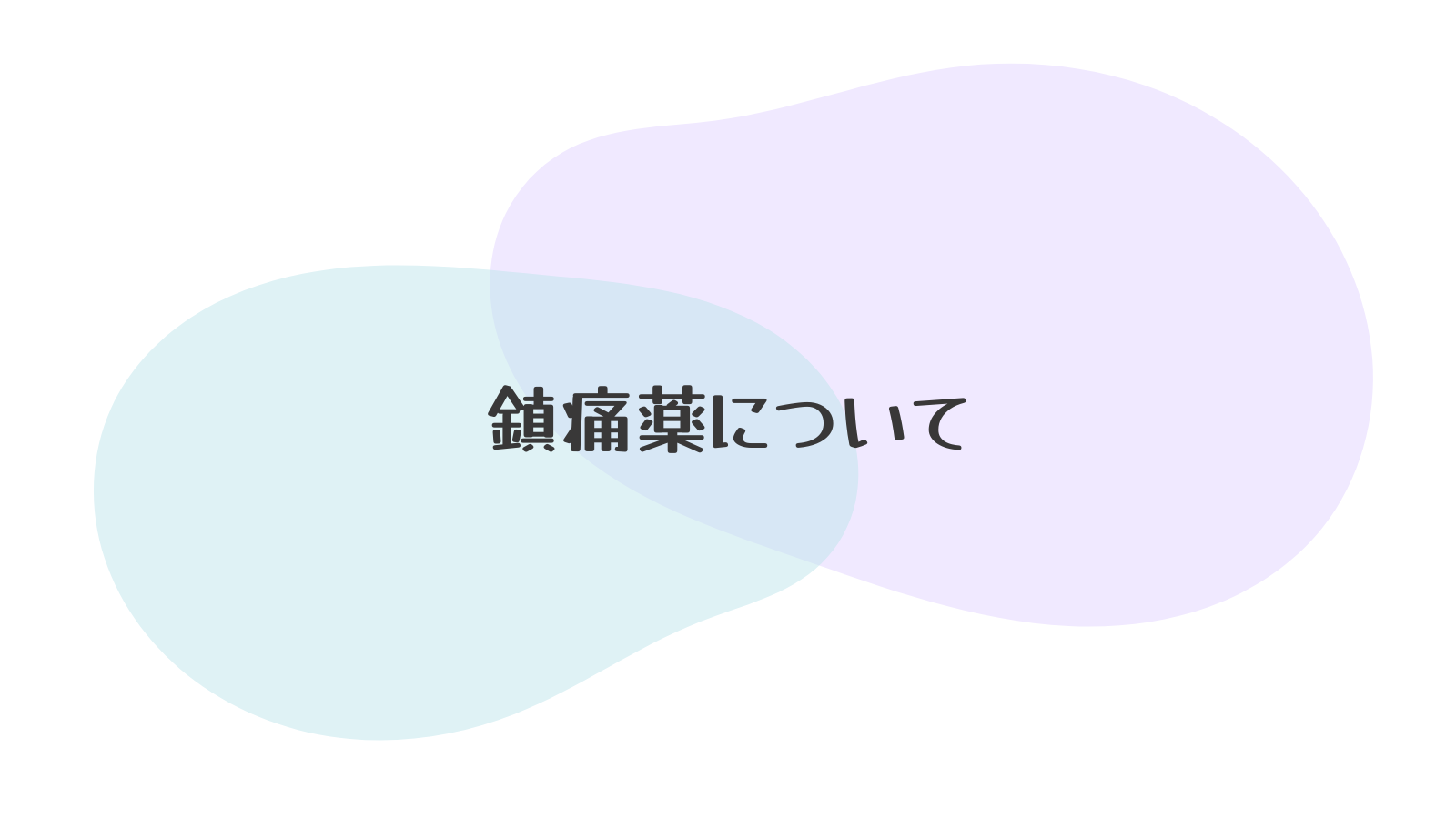

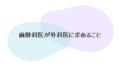
コメント