全身麻酔で使用することが多い静脈麻酔薬について書いていきます。
静脈麻酔薬の種類
現在臨床で使用されることの多い静脈麻酔薬を紹介します。
- プロポフォール
- チオペンタール(ラボナール)
- ミダゾラム
- ケタミン
- デクスメデトミジン(プレセデックス)
- レミマゾラム(アネレム)
全身麻酔の時には、主に上記の静脈麻酔薬を使用することが多いのではないかと思います。
各静脈麻酔薬の特徴
プロポフォール
短時間作用型で、全身麻酔の導入・維持に使用できる
代謝が早いので、長期投与しても覚醒遅延の危険性が少ない
鎮痛作用はなし
気道反射が抑制される
制吐作用がある
脳代謝の抑制、頭蓋内圧や眼圧の低下作用あり
血管痛がある
小児で集中治療における人工呼吸中の鎮静には使用禁忌
卵や大豆にアレルギー、過敏症のある場合には使用を避ける
■全身麻酔の導入
2~2.5mg/kg
■全身麻酔の維持
4~10mg/kg/hr
TCI使用時 3.0㎍/mlで導入→入眠後は2.0~2.5㎍/mlで維持
チオペンタール(ラボナール)
超短時間作用型で、全身麻酔の導入に使用される
鎮痛効果はない
脳酸素消費量を減らして頭蓋内圧を低下させる
気管支喘息患者では発作が誘発されやすい
ロクロニウムと混合すると白濁の沈殿を生じる
血管拡張作用、心筋抑制作用があり、循環抑制を生じる場合あり
急性間欠性ポルフィリン症には禁忌
■全身麻酔の導入
4~6mg/kgを目安に、覚醒状態を見ながら少量ずつ投与していく
ミダゾラム
短時間作用型で、全身麻酔の導入・維持に使用される
全身麻酔の麻酔前投薬としても使用される
血管痛が少ない
投与時の心抑制や血圧低下が起きにくい
フルマゼニル(アネキセート)で拮抗できる
急性閉塞隅角緑内障、重症筋無力症には禁忌
■全身麻酔の導入
0.15~0.3mg/kg
■局所麻酔時の鎮静
0.02~0.04mg/kgずつ、呼吸状態を観察しながら投与
■全身麻酔の前投薬
0.08~0.1mg/kgを30分~1時間前に筋注
☆拮抗薬:フルマゼニル(アネキセート)
初回0.2mgを緩徐に静注
4分以内に覚醒が得られなければ0.1mg追加
以降、1分ごとに0.1mg追加(最大1mg)
ケタミン
全身麻酔の導入に使用される
呼吸抑制が少ない
鎮痛作用がある
心拍数、血圧、肺動脈圧を上昇させる
眼圧、頭蓋内圧を上げる
悪夢を見ることがある
緑内障、角膜裂傷、眼外傷には使用しない
頭蓋内圧亢進、脳血管障害の症例には使用しない
術後の悪心・嘔吐が多い
■全身麻酔の導入
初回量1~2mg/kgを1分以上かけて静注
必要に応じて、初回量と同量または半量を追加投与
レミマゾラム(アネレム)
比較的新しく国内承認された静脈麻酔薬
全身麻酔の導入・維持に使用される
循環抑制作用が少ない
呼吸抑制リスクが少ない
フルマゼニル(アネキセート)で拮抗できる
急性閉塞隅角緑内障、重症筋無力症には禁忌
■全身麻酔の導入
12mg/kg/hrで意識消失まで投与
■全身麻酔の維持
1mg/kg/hrで開始、上限2mg/kg/hrまでで調節
覚醒兆候があれば、最大0.2mg/kgを静注してもよい
☆拮抗薬:フルマゼニル(アネキセート)
初回0.2mgを緩徐に静注
4分以内に覚醒が得られなければ0.1mg追加
以降、1分ごとに0.1mg追加(最大1mg)
デクスメデトミジン(プレセデックス)
全身麻酔と局所麻酔の補助として使用される
弱く鎮痛作用がある
呼吸抑制はほとんどない
徐脈、血圧低下もしくは上昇を起こすことあり
■初期負荷投与
6㎍/kg/hrで10分間投与
■維持投与
0.4㎍/kg/hrを目安に、0.2~0.7㎍/kg/hrで調節
TIVAについて
上記の静脈麻酔薬の中で、
全身麻酔の「維持」に使用されるものがいくつかありました。
多くの病院では、全身麻酔の際に、
①静脈麻酔薬で導入(眠らせる)
②吸入麻酔薬で維持
のパターンが多いのではないかと思いますが、
全身麻酔の維持も静脈麻酔薬で行う、
total intravenous anesthesia(TIVA)で全身麻酔を行うこともあります。
TIVAが適している手術には、
・神経手術
脳血流の自己調節能を温存できる
運動誘発電位モニタリングへの影響が小さい
・肺手術
一側肺換気の際に働く低酸素性肺血管収縮(HPV)を抑制しにくい
・心臓手術
人工心肺中は一般的にTIVAが用いられることが多い
・術後悪心・嘔吐 postoperative nausea and vomiting(PONV)のリスクが高い症例
PONVのリスク因子である揮発性麻酔薬を使わず、
プロポフォールの制吐作用も期待できる
・小児症例
プロポフォールでは、セボフルランでしばしばみられる覚醒時興奮やPONVが少ない
などがあり、
運動誘発電位モニタリングを使用するため、執刀医からTIVAを希望されることもありますが、
麻酔科医の好みで吸入麻酔薬かTIVAかを選択することが多いと思います。
まとめ
以上、よく使う静脈麻酔薬についてまとめてみました。
それぞれの静脈麻酔薬には特徴と注意点があります。
麻酔の維持としても、
吸入麻酔薬を使用するかTIVAで行うかという選択があることも頭にあるといいですね。
状況や症例によって使い分けることが大事ですが、
私自身も、どの薬を使用するのが適切なのかまだまだ迷うことが多いです。
少しずつ勉強して、安全に全身麻酔の導入・維持ができるようになっていきたいと思います!
次回は筋弛緩薬について勉強していこうと思います♪
ではでは~

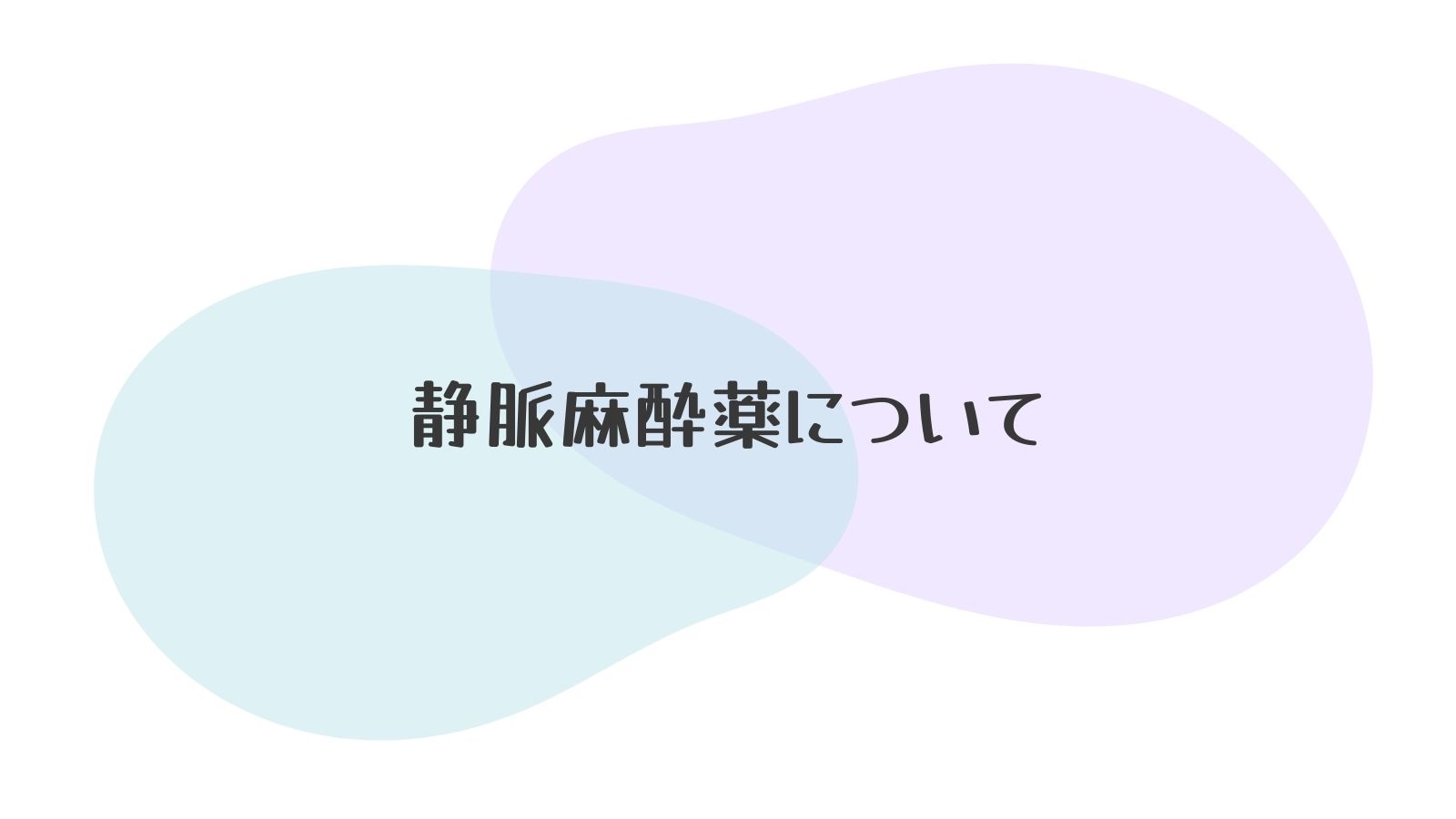
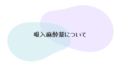
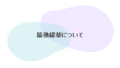
コメント