ここでは、外科から麻酔科に転科したことで、
外科医としての経験が麻酔科にどう活きているかを私なりにまとめます。
手術の流れがわかる
まず一つは、「手術の流れがわかる」ということです。
手術では、
出血や臓器損傷などが起きやすい行程、
血圧や呼吸の変化が起きやすい行程、
特に危険なことは起きにくい行程
など、様々なタイミングがあります。
手術を執刀する術者は、
今行っていることに関して理解しているはずですが、
麻酔科として外から手術を見ていると
その緊張感が伝わりにくい時もあります。
それでも麻酔科医として患者さんの全身状態を管理する以上、
術野で今何が行われていて、
身体にどういう変化が起きやすいかを
先に認知して行動できることは、とても強みになります。
実際私も、
消化器外科の手術で麻酔を管理する時には、
「次はこういう流れで進んでって、あとこれくらいの時間で終わりそうだな」
と、予想ができるので、
危険なことが起きそうな時には先回りして麻酔の調整ができますし、
手術の終わりに向けても麻酔薬の調整ができます。
ただ、どの手術でも流れがわかるわけではなく、
以前に勤務していた病院では、乳腺外科にも携わっていたので、
消化器外科手術と乳腺外科手術の時という限られた症例しか理解が及んでいない
というのが現時点での課題です。
それ以外の手術は、まだ正直何をしているかわからないのが本音です。。泣
外科医の求めていることがわかる
私自身、まだまだ麻酔科医としてはかけだしで、
どちらかというと、頭の中は外科医の考え方で物事を考えてしまうことが多いです。
いままで、外科医として手術をしていると、
「こうして欲しいな~」とか、
「これはしないで欲しいな~」など、
麻酔科への要望というのが少なからずありました。
それでも、そういう要望があるということは、
主治医としては、治療に関して大事なことだと考えて言っているわけで、
麻酔科医がすぐに諦めていいものではないと思っていますし、
なるべく要望には応えたいと思っています。
ただ、麻酔科医的にはすべてを実現することが難しい場合もあって、
お願いすると顔をしかめるような麻酔科の先生も中にはいましたので、
担当してくれている麻酔科医によっては
要望を口にできないこともありました。
なので自分は麻酔科医として、気の知れた先生に対して、
積極的に「どういうことをしてもらうとうれしいか」を聞くようにしますし、
それをなるべく実現できるようにしていこうと努力しています。
病院のシステムや状況によってはできないことも多いので、
今は「自分の中の引き出しとして抱えている」
だけのものも多いですが、、、
ここからは私の経験談なのですが、
私が麻酔科になると決めた時に、
「これはやりたい!」と思っていたことがありまして、
それは、
鼠径ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニアなど外科的なヘルニア修復術の麻酔終了時に、
なるべくバッキングさせずに抜管する
でした。
一般の方には、難しくて何を言っているのかわからないと思いますが、
(バッキングは気管にチューブがあることで起きる咳反射と思ってください)
自分が外科医として手術していた時には、
けっこう強い要望だったんです。
術後の抜管時にバッキングしてしまい、その腹圧で、
メッシュがずれる、
組織修復した糸が切れて再発する、
という症例を外科医時代に見たり経験したりしていましたので、、、
麻酔科医になってから、指導医の先生にこのことを伝えてみたら、
一刀両断されました。。。
それは外科医の手術が甘いんだ、とか、
一生患者さんは咳をしちゃいけないのか、とか、、
それ以来、そのことについてその先生には相談できなくなってしまいました。笑
私の技量が足らなかったのだと言われたらそうなのかもしれませんが、
実際、ヘルニアを先進的に行っている施設でも、
再発するタイミングとして、
抜管時のバッキングは影響が大きいと認識されていましたので、
麻酔科医としても気を付けるべきことなのかなと今でも思っています。
こういった、
外科医と麻酔科医の意見の食い違いというのはどんな手術にもあると思いますが、
自分の知っている手術に関しては、
言われずとも身をもって理解はできているつもりですので、
そこに関しては自分の強みとして持ち続けていこうと思います。
顔見知りが多い
この利点はパンチとしては弱めになりますが、
外科医として、いくつかの病院を転々としていましたし、
県内の外科医については、
学会や同門会(医局の集まりみたいなもの)で顔を合わせることもありましたので、
麻酔科医として別の病院のバイトに行っても、
知ってる先生がいるのは安心感がありました。
初めての病院で手術をするとか、麻酔をするとか、
100%の実力が出しにくい場面でもやらなくてはいけないときもありますが、
そんな時に、
知っている人がいて、
落ち着いた精神状態で、
必要な物品の場所も聞ける
という状況であることがどれだけ心強いか。
人付き合いはあまり上手な方ではないと自覚していますが、
今までの自分に感謝した瞬間でした。
外科医経験が活かせない部分
逆に、外科医の経験があまり活かされないと思うところもいくつかあります。
- 解剖の知識
- 外科専門医
まずは「解剖の知識」です。
外科医は、手術を主な生業としているので、
手術をする部位やその周辺の解剖学的知識は豊富です。
周囲の血管の走行だとか、
神経の走行だとか、
臓器と臓器の位置関係だとか、
手術するうえでは、解剖の知識は超重要で超必須です。
ただ、麻酔科では、解剖の知識はあまり活きる場面は少なく、
むしろ、薬理学や生理学など、
別の分野の知識が重要になってきますので、
これからも勉強の日々になることが確約されてしまいました。。泣
また、「外科専門医」も今は使う場面がありません。
当たり前ですが、外科専門医を持っていたとしても、
麻酔科医として働いている以上、
外科専門医が力を発揮する場面は今のところありません。
外科のバイトをするとなったら活かされるかもしれませんが、
今後更新できるのかも微妙なところです。
(経験者や知識がある方がいれば教えてください笑)
まとめ
以上、外科医から麻酔科医になって、
外科医経験が活きた部分と、活きていない部分をざっくりと紹介しました。
どの診療科からどの診療科へ転向したとしても、
今までの経験が全く活きないなんてことはないと思っています。
もちろん、新しい分野で活躍するためには、
新しい知識が必要ですし、
その分勉強が必要になることは覚悟しないといけません。
それでも転科先が肌に合わなければ、
元の診療科に戻るという選択肢も私は悪くないと思っています。
それは決して、
「ドロップアウトして戻ってきた」のではなく、
「一つ経験を増やして帰ってきた」のだと私は考えています。
私の麻酔科医人生はまだまだ始まったばかりで、
今後どのように進むのか、
はたまた外科医に戻るのか、わかりませんが、
現在の診療科から別の診療科へ転科を検討している先生へ、
また、今後の進路について悩んでいる初期研修医の先生へ、
少しでも私の経験が参考になってくれれば幸いです。
ではでは~

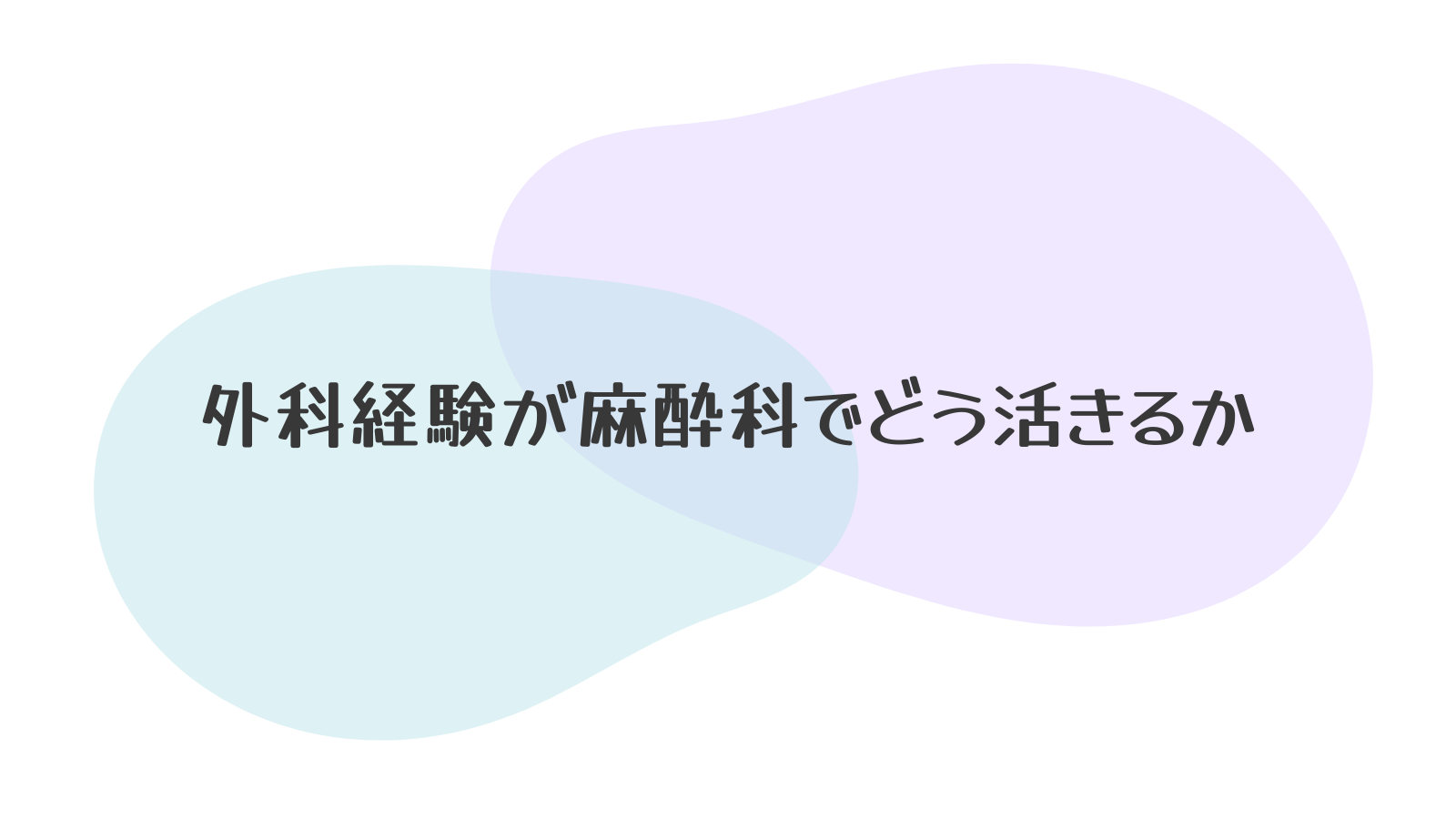
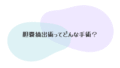
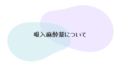
コメント