術前内服薬
・α2作動薬
例)カタプレス、ワイテンス、アルドメット、メチルドパ
・β遮断薬
例)メインテート、ビソノ、テノーミン、インデラル、セロケン、ロプレソール、ハイパジール
・ACE阻害薬
例)コバシル、レニベース、タナトリル、エースコール
ARB
例)カンデサルタン、バルサルタン、テルミサルタン、ブロプレス、ミカルディス、ディオバン、アバプロ、アジルバ
・Ca拮抗薬
例)アムロジピン、ノルバスク、ニフェジピン、アダラート、アテレック、ニカルジピン、ジルチアゼム、ヘルベッサー、ワソラン、ベラパミル
●α2作動薬、β遮断薬
急に中止するとリバウンド現象により交感神経系の亢進
→→ 周術期は内服継続を推奨
●ACE阻害薬、ARB
→→ 内服継続(2014年 AHAによる非心臓手術を予定された患者の周術期心血管評価と管理のガイドライン)
→→ 術中の低血圧予防のため、術前中止の意見もあり
●Ca拮抗薬
→→ 継続が推奨
●利尿薬
→→ 基本的には継続が推奨
麻酔において
●全身麻酔
全身麻酔導入すると交感神経を抑制
→→ 血管拡張、血圧低下
●区域麻酔(硬膜外麻酔、脊髄クモ膜下麻酔)
麻酔の効果が広がる区域において交感神経の遮断
→→ 広範囲の麻酔では血圧低下を引き起こすこともあり
麻酔導入時
■血圧低下について
術前の食事制限、飲水制限に加えて利尿剤の使用継続などあれば脱水傾向強くなっている可能性が高い
麻酔薬投与による血管拡張により血圧低下がおきやすい
↓
麻酔薬の投与は最小限に、導入前に十分な補液で脱水補正
■血圧上昇について
喉頭展開、気管挿管時は刺激が強い
↓
血圧上昇、頻脈がおきやすい
予防のため、オピオイドや吸入麻酔薬の使用を推奨
術中管理
収縮期血圧よりも平均血圧の重要性が注目されている
■血圧管理の目標
収縮期血圧:80mmHg
平均血圧:60mmHg
高血圧患者、高齢患者
↓
脳血流の自動調節能が高血圧側にシフト、臓器の慢性障害のため自動調節能の下限が高い
↓
正常血圧でも血流障害の可能性あり、臓器灌流確保のためやや血圧高めで維持
覚醒、抜管時
覚醒、抜管に伴い心拍数、血圧の上昇がみられる
周術期の循環変動では頻脈が最も心筋虚血を誘発する
術中使用した降圧薬やβ遮断薬は抜管後まで継続する
■抜管時の高血圧予防
レミフェンタニルの少量持続投与を抜管時まで継続
術後管理
疼痛などのストレスのため血圧上昇していることが多い
降圧薬よりもまずは症状改善を
術前内服していた降圧薬は経口摂取でき次第、速やかに内服再開する

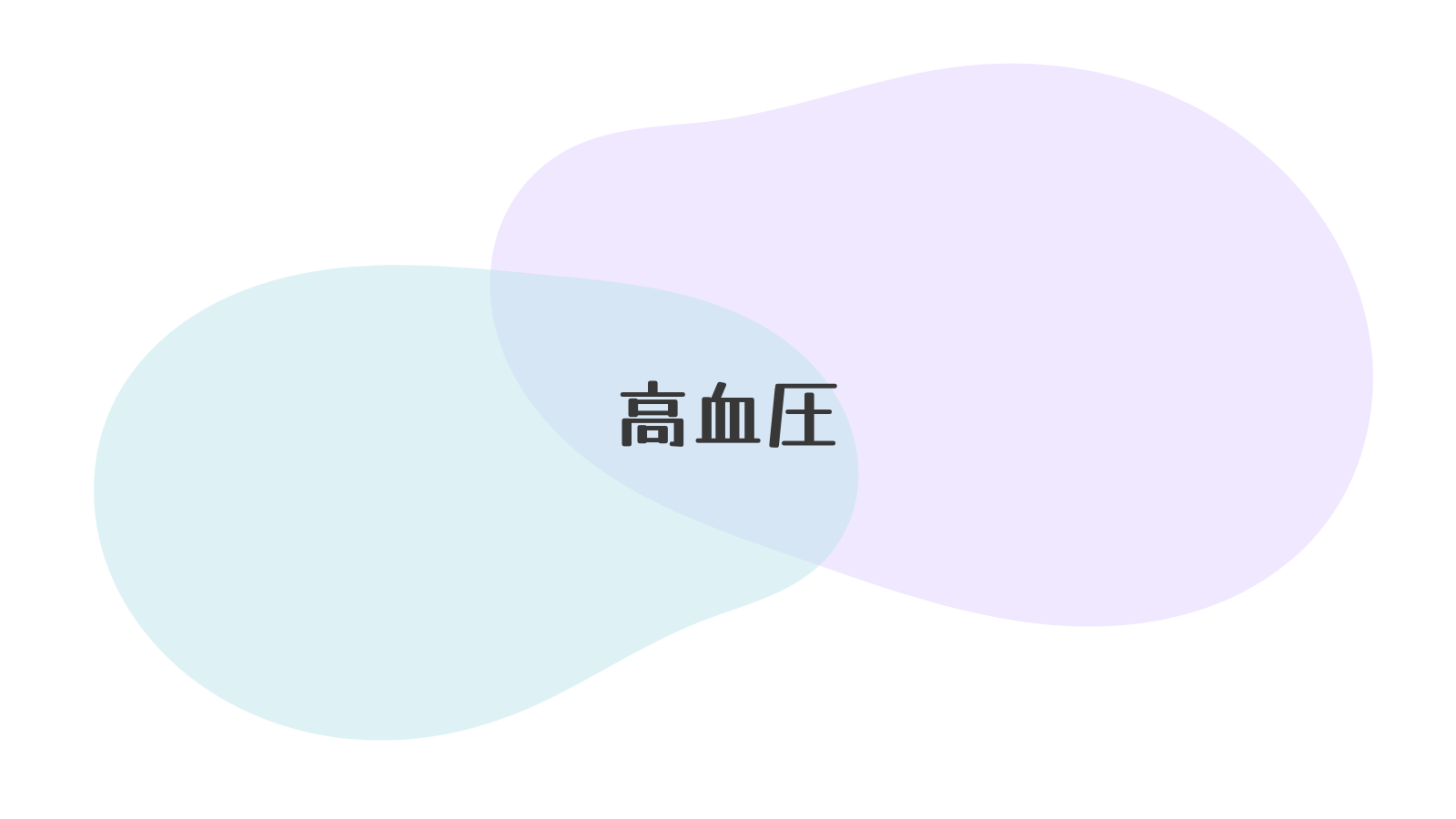
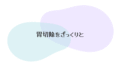
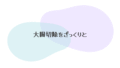
コメント