今回は脊髄くも膜下麻酔についてです!
麻酔科医として勤務し始めて、
やっぱり全身麻酔をすることが多いけど、
帝王切開や全身麻酔のリスクが高い症例など
脊髄くも膜下麻酔が必要なケースがちらほらあります。
そんな時に、
局所麻酔薬の量や穿刺部位など
思い出せないことやわからないことが多々あるので
今回勉強していこうと思います!
脊髄くも膜下麻酔とは
脊髄くも膜下麻酔とは、
くも膜下腔に局所麻酔薬を注入することで、
自律神経、知覚神経、運動神経を麻痺させる麻酔法です。
主に、下腹部や下肢、帝王切開など
下腹部以下の短時間手術で適応になります。
穿刺の高さとデバイス
脊髄くも膜下麻酔を行う際には、
脊髄損傷を起こさないようにL3-4以下から穿刺を行うことが多いです。
その際、高さの指標になるのが、
両側腸骨稜を結ぶ線である『Jacoby線』がL4棘突起上にあること。
穿刺には、Quincke型やpencil point型の25G以下の針を使用します
脊髄くも膜下麻酔の実際
では、実際にどういった流れで手技を行うか見てみましょう。
■体位
体位は基本的には側臥位です。
会陰部や肛門部の手術、高度肥満の方の場合は、
坐位で行うこともあります。
■手技
①穿刺部位を決定
②穿刺部位を中心に広い範囲に消毒する
③清潔な布やビニールをかける
④穿刺部位の皮膚に局所麻酔を浸潤させる
⑤できるだけ細い脊麻針(25G程度)を刺入させる
⑥硬膜を貫いたら脳脊髄液の逆流を確認する
⑦ベベルを回転させても逆流があれば局所麻酔薬を注入する
⑧脊麻針を抜く
手技自体はあまり難しいものではないですが、
患者さんが覚醒している状態で行うので、
一つ一つの動作を声掛けしながら行うと
患者さんの不安が少しは軽減されると思います。
皮膚に局所麻酔を浸潤させる時とか、
脊麻針を進めていく時には、
痛みで患者さんが「ビクッ!」って動く時があるので、
患者さんにはできるだけ動かないように声掛けしますが、
手技する側は急に動かれても大丈夫なように
ゆっくり丁寧に針を動かすことが重要だと思います。
必要な麻酔の高さ
体表の感覚神経の指標
- Th4 … 乳頭
- Th6 … 剣状突起
- Th10 … 臍部
- L1 … 鼠径部
上記の感覚神経の高さを指標に麻酔範囲を確認します。
各手術における麻酔の高さ
- 開腹手術 … Th4
- 経尿道・経膣手術 … Th10
- 鼠径ヘルニア手術 … Th10
- 下肢手術(ターニケットあり) … Th10
- 下肢手術(ターニケットなし) … Th12
- 直腸・肛門手術 … S1
- 前立腺生検 … S2
手術の時にこれくらいの高さまで麻酔が効いていればいいよねという目安です。
穿刺するのはL3-4あたりなので、
高比重の局所麻酔薬を注入した後、
麻酔の高さが足らない場合は
頭低位にすることで麻酔の高さを上げることができます。
仰臥位の状態では脊椎の生理的弯曲によって、
L3がもっとも高い位置にあり
Th5がもっとも低い位置になります。
なので、
高位まで麻酔を広げたい場合はL2/3やL3/4、
低位まででいい場合はL4/5での穿刺が効果的といわれています。
効果判定方法
神経遮断の順番は、
交感神経→温覚→痛覚→触覚→圧覚→運動神経となります。
くも膜下腔に局所麻酔薬を注入してから、
3~5分後に麻酔がどれくらいの高さまで効いているかを確認しますが、
確認方法には以下の方法があります。
■Cold test
酒精綿、凍った保冷材やボトルなどで冷たさを感じさせることで、
温覚の消失範囲を確認
■Pin prick test
爪楊枝や細い針の先端でチクチク感を与えることで、
痛覚、触覚、圧覚の消失範囲を確認
いずれかの方法で麻酔高を確認し、
もう少し範囲が広く欲しい場合には頭低位にしたり
左右どちらか片方に効いている場合には軽く側臥位にしたりして
麻酔の範囲を調整することもあります。
使用する薬剤
■0.5%ブピバカイン(マーカイン)
高比重と等比重がある
高比重では、患者体位を頭低位にすることで麻酔高を上げられるため調節性に優れる
▼高比重
・用量 2~3ml
・作用時間 90~180分
▼等比重
・用量 3~4ml
・作用時間 120~200分
■フェンタニル
即効性が高い
術中の腹膜刺激による嘔気にも効果あり
・用量 10~25㎍(0.2~0.5ml)
・作用時間 4~6時間
■モルヒネ
作用発現までの時間が長い
術後の遷延性呼吸抑制に注意が必要
・用量 100~200㎍
・作用時間 12~24時間
合併症について
硬膜穿刺後頭痛(PDPH:post dural puncture headache)
硬膜から脳脊髄液が漏れることで髄圧が低下し
硬膜や血管、神経の牽引によって引き起こされる頭痛のことをいいます
20~40歳代の女性に多い
■対策
pencil point型のなるべく細い脊麻針を使用する(25G以下)
Quincke型であれば、ベーベルを体軸と平行に穿刺する
■治療
保存的治療(安静、水分補給、輸液負荷、カフェイン内服)
硬膜外腔へ生理食塩水、自己血(約10ml程度)を注入
全脊髄くも膜下麻酔
麻酔レベルがT4以上の高位になると、
T1~4の心臓交感神経がブロックされ、低血圧・徐脈が顕著になってきます
C4(横隔神経)の高さまでブロックされると、
横隔膜の麻痺により呼吸困難が生じる
脳幹にまで麻酔レベルが達すると、
意識消失が生じる
■治療
低血圧・徐脈 → アトロピン、エフェドリン
横隔膜麻痺 → 酸素投与、気道確保、人工呼吸
馬尾症候群
穿刺時の神経外傷や局所麻酔薬の神経毒性による
下部脊髄神経線維の障害で、
膀胱直腸障害、会陰部知覚障害、下肢麻痺が生じることがあります
■対策
穿刺中に臀部から下肢にかけての放散痛があった場合、
脳脊髄液の逆流がない場合や血液が混入している場合、
いずれにおいても局所麻酔薬の注入はせずに抜針する
麻酔方法を切り替えることも検討する
一過性神経症状(TNS:toransient neurologic symptoms)
穿刺時には明らかな神経外傷がないにも関わらず、
局所麻酔薬の神経毒性による神経障害として、
麻酔の回復から24時間以内に臀部から下肢に放散痛が生じることがあります
通常は数日~1週間程度で消失します
■対策
血管収縮薬は添加しない
再穿刺・再投与する際は部位を変更する
脊椎病変(脊柱管狭窄症など)を有する患者には施行しない
感染・血腫
発熱、穿刺部位の持続する疼痛などを認める場合は、
穿刺部の感染や脊髄硬膜外血腫を疑います
■対策
清潔操作の徹底
抗凝固療法中の患者へは、別の麻酔方法も検討する
『抗血栓療法ガイドライン』では、
血小板数が5万/㎕以上あれば施行可
となっていますが、
その他凝固能や内服中の薬剤によっても検討が必要です。
血小板数以外にも凝固能も含めて、
PT-INR 1.5 未満
APTT 50 秒未満
血小板数 10万/mm3以上 or 70万/mm3以下
としている施設もあります。
■治療
抗生剤投与
減圧術が必要な場合もある
まとめ
以上、今回は脊髄くも膜下麻酔について勉強しました。
穿刺部位や麻酔の高さなど私も勉強になる部分が多かったです。
適切な脊麻針で合併症なく麻酔を安全にしていきたいと思います♪
次回は硬膜外麻酔について勉強していく予定です!
ではでは~

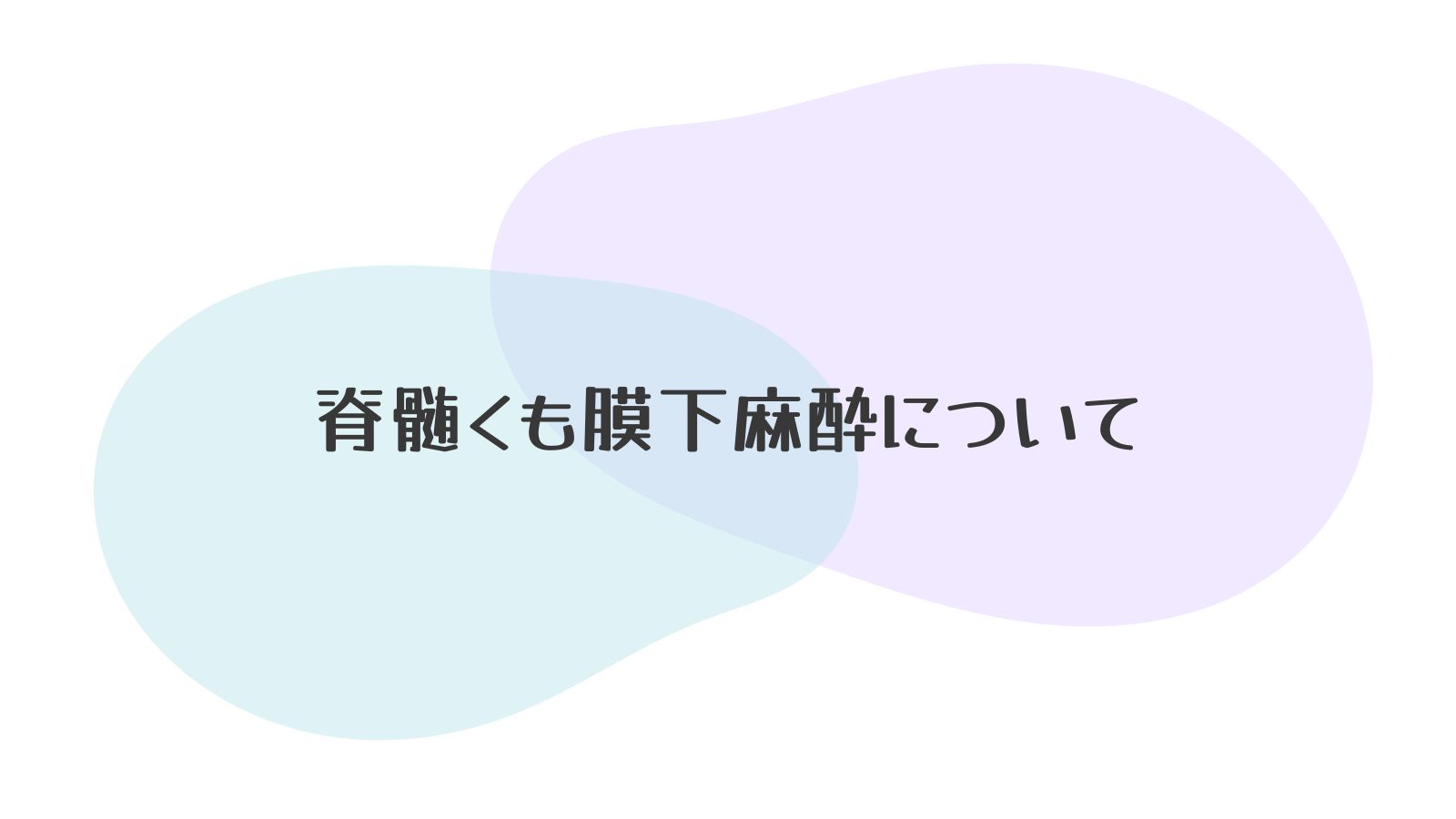
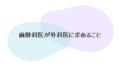
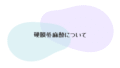
コメント