今回は硬膜外麻酔についてです!
脊髄くも膜下麻酔よりも
適応範囲が広く、
術後鎮痛としても汎用性が高いので、
使う頻度としてはわりと多いと思います。
よく使う麻酔法だからこそ、
よくわからないけどなんとなくできている
みたいな状況を打開したいと思います!
硬膜外麻酔とは
硬膜外腔に局所麻酔薬を注入することで、
痛みを含む脊髄神経の伝達を遮断する麻酔方法のことをいいます。
脊髄くも膜下麻酔と比べて、
『運動神経遮断作用が軽度で、どの脊椎の部位でも使用しやすい』という特徴があり、
①全身麻酔の術後鎮痛として使用
②ペインクリニック外来の治療として慢性疼痛に対して使用
③四肢の血流障害の治療として使用
など、
手術のためだけなく
いろいろなところで使用されています。
硬膜外麻酔のメリット・デメリット
メリット
カテーテルにより術後持続投与ができる
運動神経は残しながら鎮痛効果が得られる
オピオイド使用量を削減できる
PCAポンプで患者本人が疼痛コントロールできる
デメリット
手技の難易度がやや高い
合併症のリスクあり
症例によってはカテーテル自己抜去のリスクあり
硬膜外麻酔の流れ
■体位
処置の体位は脊髄くも膜下麻酔と同様に基本的には側臥位です。
肥満患者では、坐位で行った方が正中を確認しやすいこともあります。
この際、「膝を胸につけて丸くなる姿勢」をとれると、
棘突起間が広がるため成功確率が上がります。
■手技(抵抗消失法)
①穿刺部位を決定
②穿刺部位を中心に広い範囲に消毒する
③清潔な布やビニールをかける
④穿刺部位の皮膚に局所麻酔を浸潤させる
⑤硬膜外針を刺入させる (詳しくは後述)
⑥黄靭帯の抵抗を感じたら内筒を抜いて注射器を接続
⑦注射器の抵抗が消失したところで硬膜外カテーテルを挿入
⑧カテーテルを残して硬膜外針のみ抜去
行程としてはこんな感じです。
穿刺法
硬膜外針を刺入させる方法ですが、
棘間の正中を刺入する正中法と、
正中の1横指程度外側から刺入する傍正中法があります。
■正中法
頸椎、腰椎で選択することが多い
患者正中に位置する棘上靭帯を左手示指と中指で固定
硬膜外針を皮膚にほぼ垂直に刺入させる
棘上靭帯、棘間靭帯に到達した時点で硬膜外針は固定される
さらに黄靭帯まで到達し、貫通して抵抗がなくなることで硬膜外腔を確認
■傍正中法
胸椎で選択することが多い
高齢者や脊椎変形のある患者、正中法で困難な場合にも選択する
棘間の1~1.5㎝(約1横指)外側から刺入させる
脊柱管の中心に向けて、やや頭側に硬膜外針を進める
黄靭帯に到達すると硬膜外針が固定される
貫通して抵抗がなくなることで硬膜外腔を確認
カテーテルの挿入
ほとんどの症例で、
術後鎮痛も兼ねて硬膜外カテーテルを挿入すると思います。
硬膜外針が硬膜外腔に到達したら、
皮膚から硬膜外腔までの深さを確認した後、
硬膜外カテーテルを挿入していきます。
カテーテルがスムーズに挿入できればOKです。
抵抗があれば硬膜外腔に入っていない可能性があるので、
硬膜外針を刺入し直す方が良いです。
15cmくらいまでカテーテルを挿入したら硬膜外針のみを抜き、
硬膜外腔に3~5cm程度カテーテルが留置されるように
カテーテルの深さを調節します。
(皮膚から硬膜外腔までの深さ + 3~5cm)
カテーテルにコネクタを接続して
逆血や脳脊髄液の逆流がないことを確認したら
2mlの局所麻酔薬を注入して
くも膜下腔や血管内ではないことを確認します。(test dose)
麻酔の高さ
脊椎くも膜下麻酔と同様に硬膜外麻酔も、
手術する部位、臓器によって穿刺やカテーテル留置の高さを変えます。
脊椎レベルの指標
- C7 … 第7頸椎(最も突出している頸椎)
- Th3 … 肩甲棘
- Th7 … 肩甲骨下角
- L4 … 両側腸骨稜を結ぶ線(Jacoby線)
- S2 … 両側下後腸骨棘を結ぶ線
これらを指標にして
穿刺する高さの棘突起を確認していきます。
各手術における穿刺部位の目安
- 食道手術 … Th4~6
- 上腹部手術 … Th7~10
- 下腹部手術 … Th10~L1
- 直腸手術 … L2~3
- 帝王切開 … Th10~12
- 子宮全摘 … L1~3
- 鼠径ヘルニア … L2~3
- 下肢手術 … L2~4
- 無痛分娩 … L2/3 or L3/4
腹腔鏡手術だと、
臍部とその他のポート配置によっても
穿刺部位を変更することになります。
おおむね皮膚切開部位に対応した高さでの穿刺ですが、
硬膜外カテーテルが頭側に向かって留置されることを考えると、
私の感覚的には、
『皮膚切開の支配神経よりも少し低めで穿刺』
くらいがちょうどいい塩梅かなと思ってます。
臓器の支配神経はそれよりも少し高めであることが多いです。_
使用する薬剤
■1~2%リドカイン
短時間作用型
■1~2%メピバカイン
短時間作用型
■0.2~0.375%ロピバカイン(アナペイン)
長時間作用型
術後鎮痛としても使用される
■0.125~0.25%レボブピバカイン(ポプスカイン)
長時間作用型
術後鎮痛としても使用される
■フェンタニル
▼術中
単回投与 25~100㎍
持続投与 25~100㎍/hr(0.5~1.0㎍/kg/hr程度)
▼術後
単回投与 4~50㎍
持続投与 4~30㎍/hr
■モルヒネ
単回投与 2~6mg/回
持続投与 2~10mg/日
私が勤務している病院では、
術中使用
→ 1.5%リドカイン
術後の持続投与
→ 0.2%アナペイン or 0.2%ロピバカイン + フェンタニル
を使用しています。
合併症
硬膜穿刺、カテーテル迷入、全脊髄くも膜下麻酔
硬膜外腔の確認が難しい場合、
誤って硬膜まで穿刺してしまうことがあります。
硬膜外針は比較的太いので、
硬膜を穿刺した部位から脳脊髄液が流出して
硬膜穿刺後頭痛が出現する可能性が高くなります。
また、硬膜穿刺をしたことに気付かずにカテーテルを留置した場合、
くも膜下腔にカテーテルが迷入して留置されることになり、
局所麻酔薬をくも膜下腔に大量に注入することで全脊髄くも膜下麻酔となり
呼吸困難や意識消失などをきたす可能性もあります。
◆対策
硬膜外針の内筒を抜いた時、
硬膜外カテーテルを留置した後に、
脳脊髄液の流出や逆流を確認する。
脳脊髄液の流出が確認された場合は、
原則的には再穿刺はしない。
感染・血腫
硬膜外腔には豊富な血流が分布しているため、
硬膜外針やカテーテルにより血管を損傷することで
血腫を作ってしまうことがあります。
血腫から感染を起こして膿瘍化してきたり、
留置したカテーテルから感染を引き起こすこともあります。
血腫や膿瘍により
腰背部痛、下肢痛、運動機能障害、膀胱直腸障害などを起こすことがあり、
治療には、原因となっているカテーテルを抜去し、
血腫除去術や除圧術が必要になることもあります。
抗血栓薬内服患者や凝固能異常のある患者には
そもそも硬膜外麻酔が適応かどうかの見当も必要ですし、
糖尿病患者では易感染性なども考慮し、
カテーテルの管理には十分注意が必要になります。
硬膜外麻酔の適応基準は施設によって違うと思いますが、
PT-INR 1.5 未満
APTT 50 秒未満
血小板数 10万/mm3以上 or 70万/mm3以下
としている施設もあります。
カテーテル抜去時の問題
術後鎮痛として不要になったらカテーテルを抜去しますが、
棘突起による圧迫やカテーテルのからみ、周囲組織との癒着などにより
カテーテル抜去時に抵抗を感じることがあり、
そのまま強くカテーテルを引っ張ると、
カテーテルが断裂し、先端が体内に遺残する恐れがあります。
抵抗を感じる場合は、
カテーテル挿入時と同様の「丸くなる体勢」をすることで
抵抗なく抜去できることもあります。
また、必要以上に硬膜外カテーテルを留置しないようにしておくことも重要です。
まとめ
以上、硬膜外麻酔について勉強していきました!
どこから穿刺したらいいのか、、
術後の使用方法がわからない、、
そんな疑問に少しでも寄り添えればと思って書きました。
いずれは、無痛分娩の硬膜外麻酔や
小児外科の仙骨硬膜外麻酔
についても勉強していこうと思います!
次回からは末梢神経ブロックについて投稿する予定です♪
ではでは~

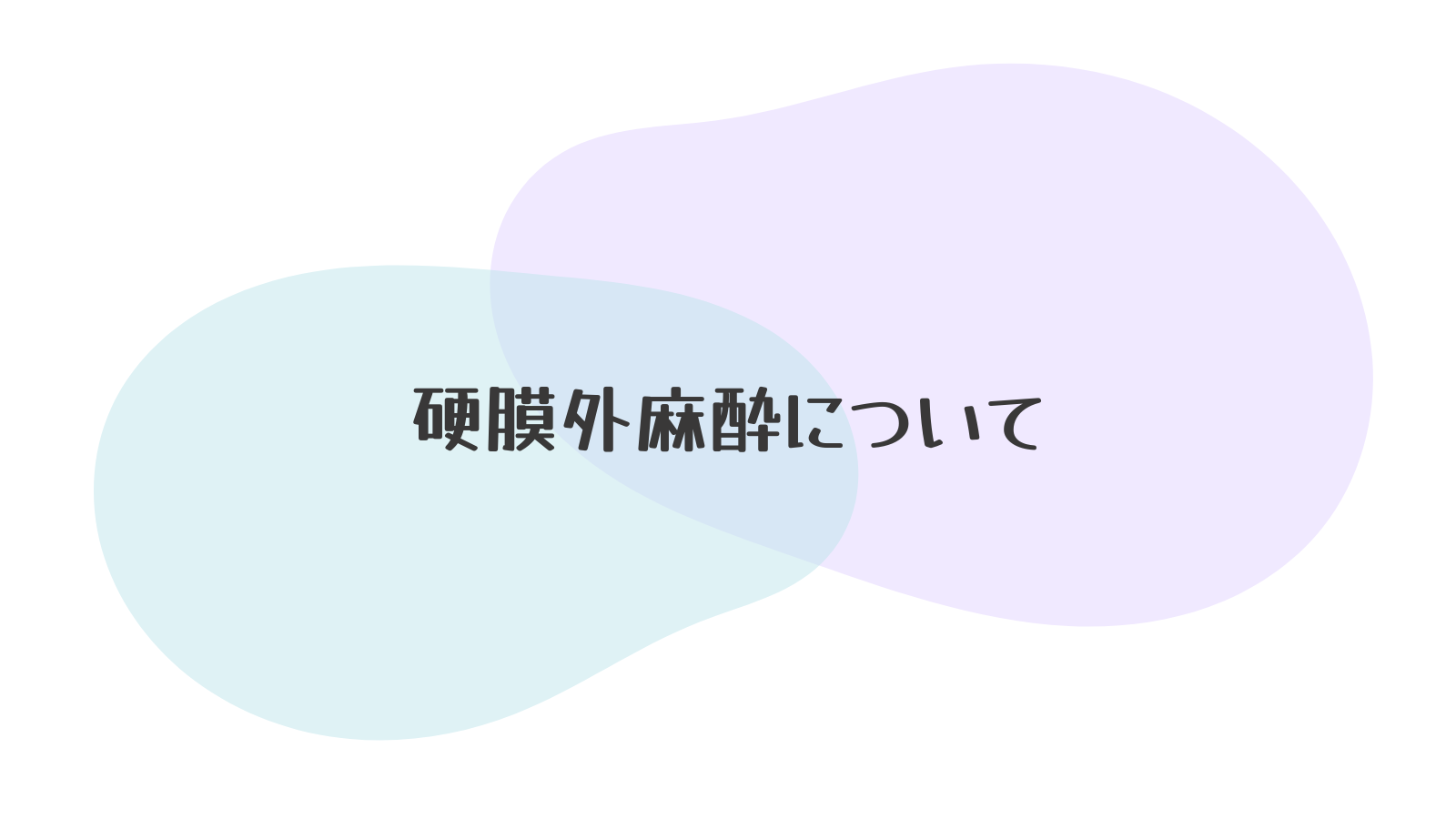
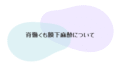
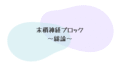
コメント