今回は末梢神経ブロックについて勉強していきます。
正直、エコーで標的とする神経がわかりにくかったり、
上手にエコーに針が映せなかったり、
どの神経がどこを支配しているかあいまいだったり、
まだまだ分からないことだらけですが、
これを機に少しでも理解を深めていこうと思います!
すべての末梢神経ブロックを1つの記事にすると
あまりにも長くなってしまいそうなので今回は総論とします。
各部位の詳細については
別記事で各々まとめていこうと思います!
末梢神経ブロックとは
末梢神経の周囲や神経が走行する部位に
局所麻酔薬を投与することで神経伝達を遮断して
鎮痛を得る方法です。
従来は、ランドマーク法や通電刺激法が行われていましたが、
エコー技術の発達により超音波ガイド下に行うことで
さらに高い成功率で安全に行うことができるようになってきました。
メリットとデメリット
メリット
・交感神経を遮断しないため、血圧低下などの循環抑制が少ない
・悪心・嘔吐が少ない
・神経遮断領域をより限局的にできる
・硬膜外麻酔に比べて脊髄レベルでの神経損傷がない
・血腫による合併症が少なく、凝固能が低下した患者でも行いやすい
デメリット
・広い範囲に鎮痛を効かせたいときに不利
・局所麻酔薬が大量に必要な場合、局所麻酔薬中毒をきたす可能性がある
・手技がやや難しく、確実な麻酔効果が得られない場合がある
・ブロックの部位によって、気胸や神経損傷、出血など合併症の可能性がある
末梢神経ブロックの種類
末梢神経ブロックの種類はいろいろなものがあり、
同じ神経をブロックするにしてもアプローチ方法が違ったり
一つの手術で複数のブロックを組み合わせることがあったりします。
どのブロックも大事だと思いますが、
めちゃくちゃ数が多いので、
独断と偏見で
使う頻度が高いものを中心に学んでいこうと思います。
■上肢
腕神経叢ブロック
斜角筋間アプローチ
鎖骨上アプローチ
鎖骨下アプローチ
腋窩アプローチ
など
■下肢
坐骨神経ブロック
臀下部(臀部)アプローチ
前方アプローチ
膝窩部アプローチ
PENGブロック
大腿神経ブロック
外側大腿皮神経ブロック
伏在神経(内転筋管)ブロック
閉鎖神経ブロック
など
■体幹
肋間神経ブロック
胸部傍脊椎ブロック
腹直筋鞘ブロック
腹横筋膜面ブロック
など
どうでしょうか
あーもう無理って思いますよね笑
ただ、いったんこのブログでは、
安全性と有効性が高く、まず習得されるべきとされている
『PLAN A blocks』という基本的神経ブロックを中心に
紹介していこうと思っています。
必要物品と手技
■超音波プローブ
超音波は高周波になるほど、空間分解能は高いが深部まで届きにくい
浅い部位(<4cm) … 高周波リニアプローブ(10MHz以上)
深い部位(≧4cm) … コンベックスプローブ(2~5MHz程度)
■ブロック針
基本的にはショートベベルの鈍針
→ 筋膜を貫いた感覚がわかりやすい、神経損傷起こしにくい
※神経刺激をする時は、先端以外が絶縁加工されたブロック針
手技
①プレスキャン
→ 目標とする神経の描出、周囲の血管の走行や臓器などを確認
②穿刺部位を消毒
③清潔にしたエコーをあてて神経を描出
④エコーガイド下にブロック針を挿入
・平行法:エコープローブに平行に針を刺入
・交差法:エコープローブに垂直に針を刺入
⑤目標に達したら吸引テストを行い、逆血がなければ局所麻酔薬を少量投与
⑥神経周囲や筋膜面に局所麻酔薬が広がれば、さらに予定量投与
局所麻酔薬の種類
リドカイン(キシロカイン)
濃度 1.0~1.5%
作用時間 60~120分
最大投与量(単神経) 200mg(1.0%で20ml)
ロピバカイン(アナペイン)
濃度 0.375~0.75%
作用時間 120~240分
最大投与量(単神経) 3mg/kg(50kgの場合、0.375%で40ml)
心毒性が弱い
メピバカイン(カルボカイン)
濃度 1.0~1.5%
作用時間 60~120分
最大投与量 7mg/kg(50kgの場合、1.0%で35ml)
表面麻酔には使用できない
ブピバカイン(マーカイン)
濃度 0.25~0.5%
作用時間 180~360分
最大投与量 2mg/kg(50kgの場合、0.25%で40ml)
運動神経より知覚神経が強く遮断される
リドカインに比べて心毒性が強い
私が現在勤務している病院では、
術後の疼痛緩和目的の末梢神経ブロックには
0.375%ロピバカインを使用しています。
術中の体動を制限するような閉鎖神経ブロックについては、
作用時間の短いキシロカインを使うことが多いです。
合併症
局所麻酔薬中毒
局所麻酔薬の使用量が多くて血中濃度が上昇した場合に出現
緩徐に血中濃度が上昇していく場合は、
口唇のしびれ・多弁・興奮
視覚・聴覚異常
意識障害・痙攣
呼吸停止
循環抑制・心停止
と、刺激症状→抑制症状の順で現れることが多いです。
誤って血管内に直接注入した場合は、
少量の投与でも症状を呈することがあり、
一気に血中濃度が上昇すると
中枢神経症状と心毒性が同時に出現することもあります。
■対策
局所麻酔薬の使用は必要最小限にとどめる
薬剤を注入するときは吸引テストを怠らない
注入は少しずつ時間を空けて行う
毒性の弱いものを選択する
■治療
・局所麻酔薬の注入を中止
・気道確保、100%酸素投与
・痙攣に対してベンゾジアゼピン投与
※循環不安定の場合は、プロポフォール禁忌
・痙攣が持続する場合は筋弛緩薬
・循環抑制には、BLS(一次救命処置)/ACLS(二次救命処置)
・20%脂肪乳剤(イントラリポス)の静脈内投与
その他合併症
・ブロック針の穿刺による神経損傷
・血管穿刺、血腫
・局所麻酔薬の血管内、神経内誤注入
・アレルギー反応
・感染 etc.
まとめ
以上、末梢神経ブロックについての
手技や局所麻酔薬など、
一般的な総論をまとめてみました。
まだまだ分からないことが多いので
今後は各部位ごとにもう少し詳しく学びたいと思います!
文章だけだとわかりづらいところもあるので、
エコーや神経支配も画像にして整理できたらと思っています♪
ではでは~

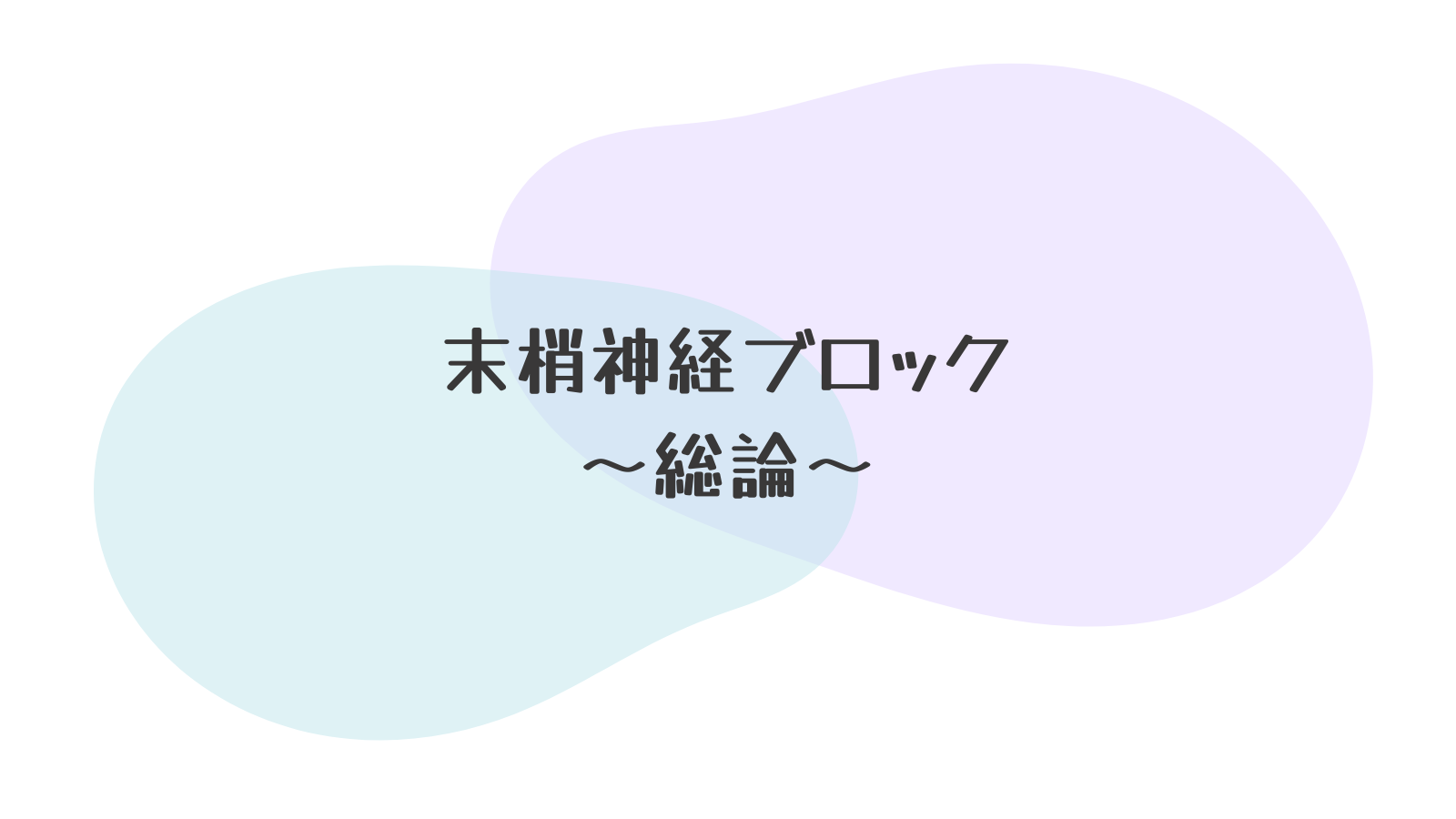
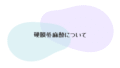

コメント