ここでは小児麻酔について、
私が学習したことをつらつらと書いていこうと思います。
小児の生理学的特徴
■呼吸器系
・酸素必要量が大きい
・舌が大きい、気管が細い、喉頭痙攣をおこしやすい
→気道閉塞をおこしやすく、気道確保も困難
・機能的残気量が少ない
→呼吸予備能が少なく、低酸素になりやすい
※小児では、低換気→低酸素血症→徐脈→心停止の時間が短い!
・喉頭がC3-4の高さに位置する(成人はC4-5)
→喉頭展開の際に深くに入りやすく、注意が必要
私個人の経験ですが、
小児の症例で、マスク換気の時にはSpO2 100%を保っていたのに、
挿管操作などで無換気の時間があると、すぐに酸素化が悪くなっていく
という経験をしました。
何事もなく麻酔を終えることができましたが、
小児麻酔における呼吸管理の重要さを痛感しました。
■循環器系
・そもそも血圧や脈拍の基準値が成人と異なる
・出生後から、胎児循環から成人型循環へ移行していく
・胎児ヘモグロビンの残存(生後数か月~6か月で成人ヘモグロビンへ置き換わる)
→SpO2が高くても、組織低酸素に注意が必要
・副交感神経が優位
→迷走神経反射により徐脈になりやすい
・心拍出量は心拍数に依存
■神経系
・脊髄下端の位置が変化する
→新生児(脊髄下端:L3、硬膜下端:S4)
幼児期(脊髄下端:L1、硬膜下端:S2) ※ここで成人と同じになる
・頭蓋内圧は成人よりも低い
※大泉門、小泉門の閉鎖までは圧が上昇しても代償される
・大泉門閉鎖:1~1歳半、小泉門閉鎖:2~3か月
・脳脊髄液、脳血流量が成人と比べて多い
・脳灌流圧の変化による脳血流量の自動調節機構はあるが、調節域は不明
■体温
新生児期
・体重あたりの体表面積が大きく、皮膚や皮下組織の断熱性が低い
→環境温による影響を受けやすいため、低体温になりやすい
・皮膚の水分含量が多く、不感蒸泄が多い
→熱喪失が大きい
・幼小児は筋肉量が少ないため、シバリングでの熱産生ができない
乳幼児期
・皮下脂肪が厚くなり、断熱性が高くなる
・基礎代謝が大きく、非ふるえ熱産生ができるようになる
・十分に放熱ができないと、体温上昇をきたすことに
小児麻酔の体温管理を学習したときに思ったこと
助産師さんからこどもの沐浴の指導を受けた際に、
「赤ちゃんは気化熱で冷えやすいから、風呂から出たら素早く体を拭いてあげてね」
と言われたことを思い出しました。
小児の麻酔をかける時には、
わが子を温めるかのように保温してあげようと思いました。
小児麻酔の導入
■緩徐導入
~大まかな流れ~
①手術室入室後、酸素+N2O → 酸素+セボフルランで入眠させる
②静脈路を確保し、筋弛緩、鎮痛薬を投与していく
③気管挿管
※N2Oは閉鎖腔に移行して膨張させるため、
イレウス、壊死性腸炎、気胸、眼内手術、腹腔鏡手術などでは使用しません。
静脈路が麻酔導入前に確保できない場合は緩徐導入となり、小児では一番使用されています。
セボフルランのにおいが気になる子は、
マスクにバニラや柑橘系、いちごなどのエッセンスをつけてあげます。
■急速導入、迅速導入
麻酔導入前に静脈路が確保できている場合は、
成人と同様に静脈から麻酔薬を投与して導入することができます。
患児一人で手術室に向かい、手術を受ける
母親や父親と離れることに不安が強い場合は、
親子同伴麻酔導入法といって、
親子で手術室まで向かっていき、
緩徐導入で患児が入眠するまで親が同伴することもあります。
最後に
自分のこどもが手術を受けることになり、不安を感じない親はいないでしょう。
私にもこどもができたことでその不安感が手に取るようにわかるようになりました。
不安に感じているのは手術を受けるこどもも一緒です。
各手術の内容、術式などについてはわかりませんが、
少しでも麻酔について理解していただき、不安の解消につながればと思います。
医学生、研修医のみなさんには、
実習、研修でわけわからず見ているのではなく、
大まかな流れだけでもつかんだ状態で見てもらえば、
興味がわく機会につながるのではないでしょうか。
ではでは~

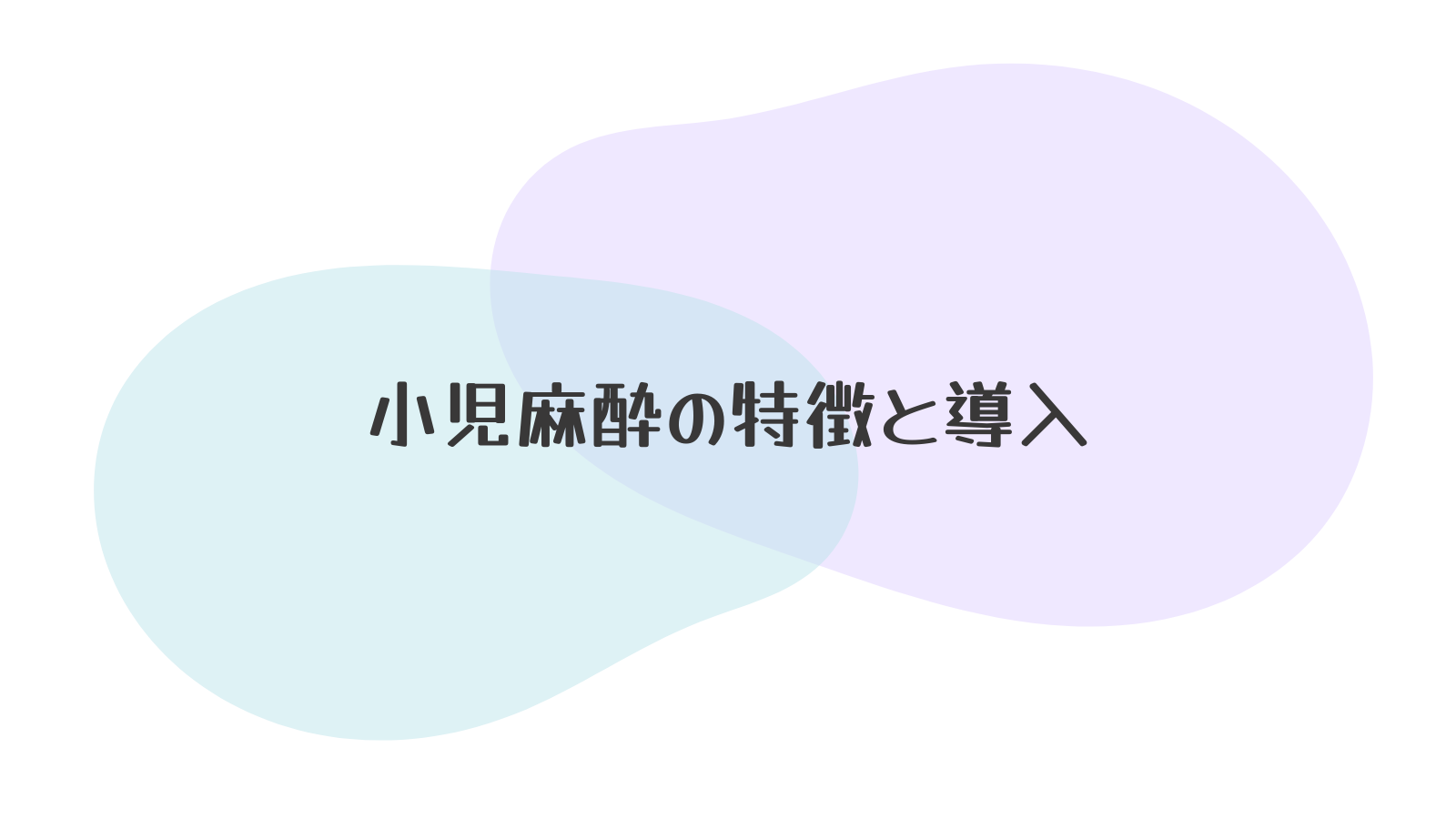
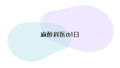
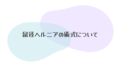
コメント