ここでは現代の全身麻酔には欠かせない吸入麻酔薬について書いていこうと思います。
何気なく使用している吸入麻酔薬について少しでも知識をアップデートしていきたいと思います。
吸入麻酔薬とは
全身麻酔の3要素である、
鎮痛
鎮静
筋弛緩
のうち、「鎮静」を担うのが吸入麻酔薬になります。
点滴から静脈麻酔薬を入れて麻酔をかけることもありますが、
麻酔深度の推測が予測しやすいことや
代謝の個人差が少ないことなどの理由から、
現在では、吸入麻酔薬を使用されることが多いと思います。
麻酔導入時から吸入麻酔薬を使用する麻酔の方法もありますが、
一般的な予定手術では、
『導入は静脈麻酔薬→維持は吸入麻酔薬』という順序の麻酔がほとんどです。
全身麻酔の時には、呼吸が止まった状態になるので、
気管挿管といって、
口から気管に気管チューブを入れて人工呼吸器で呼吸の管理をする必要があります。
その際人工呼吸器から酸素・空気・吸入麻酔薬を流して呼吸させ、
吸入麻酔薬を体内に取り込むことで鎮静が得られる
という具合です。
いろいろな吸入麻酔薬
先ほど説明した吸入麻酔薬には、いろいろな種類のものがあります。
現在、主に使用されているものは以下の3種類です。
・セボフルラン
・デスフルラン
・笑気(N2O:亜酸化窒素)
では、それぞれの特徴を見ていくことにします。
・セボフルラン
①気道刺激性が少ない
②気管支拡張作用が強い
③血液ガス分配係数が小さい
・デスフルラン
①気道刺激性が高い
②鎮痛作用はほとんどない
③筋弛緩作用がある
④血液ガス分配係数が小さい
・笑気(N2O:亜酸化窒素)
①二次ガス効果がある
②鎮痛作用がある
③呼吸抑制がほとんどない
ざっとこんな感じです。
吸入麻酔薬の使い方
次に、吸入麻酔薬の使い方についてみてみましょう。
まずは、セボフルランとデスフルランについて、
どちらも血液ガス分配係数が小さいという点では、
麻酔の覚醒が迅速
麻酔深度の調整を適切にコントロールできる
など、似たようなところがあります。
大きく違う点とすれば、やはり、
気道刺激性の強さ
です。
セボフルランは、気道刺激性が少ないため、
吸入麻酔薬のみで麻酔導入を行う緩徐導入や、
導入と維持すべてを吸入麻酔薬でおこなうVIMA(volatile induction and maintenance anesthesia)という方法が可能です。
麻酔導入前に静脈路確保が困難な小児症例や、
喘息の既往がある気道が過敏な症例などで使用されることが多いです。
それに対してデスフルランは、
術後の覚醒・回復がより早期に得られるため、
術後呼吸器合併症リスクの高い高齢者や肥満患者で有用とされています。
特にリスクもない、小児症例でもない、喘息の既往もない
といった症例については、
各麻酔科医の好みや、施設の方針で決めていることが多いのではないでしょうか。
次に、笑気について、
ひと昔前までは全身麻酔ではほぼルーティンで使われる程の使用頻度だったようですが、
①温室効果ガスである
②静脈麻酔薬や吸入麻酔薬の進歩
などの理由から、使用頻度は減ってきています。
ただ、自発呼吸が残りつつ鎮静ができ、鎮痛作用もあるということで、
・歯科治療の補助
・自発呼吸を残しながら麻酔管理をしたい症例
などで使用されることもあります。
また、『二次ガス効果』を期待して、
吸入麻酔薬での麻酔導入の際に同時投与することで麻酔導入が迅速に行えたり、
吸入麻酔薬の濃度を減らして維持することも可能となります。
まとめ
ここまで吸入麻酔薬について書いてみましたが、
ざっくりとまとめると、
ーセボフルラン → 小児麻酔、喘息患者に強い
ーデスフルラン → 覚醒が早い
ー笑気 → 使用頻度は減ってきているが、二次ガス効果としての使い道あり
という感じです。
医学生や研修医の方々、私と同じように麻酔科初学者の先生方が
吸入麻酔薬の理解に困ったときの助けになればうれしいです。
ではでは~

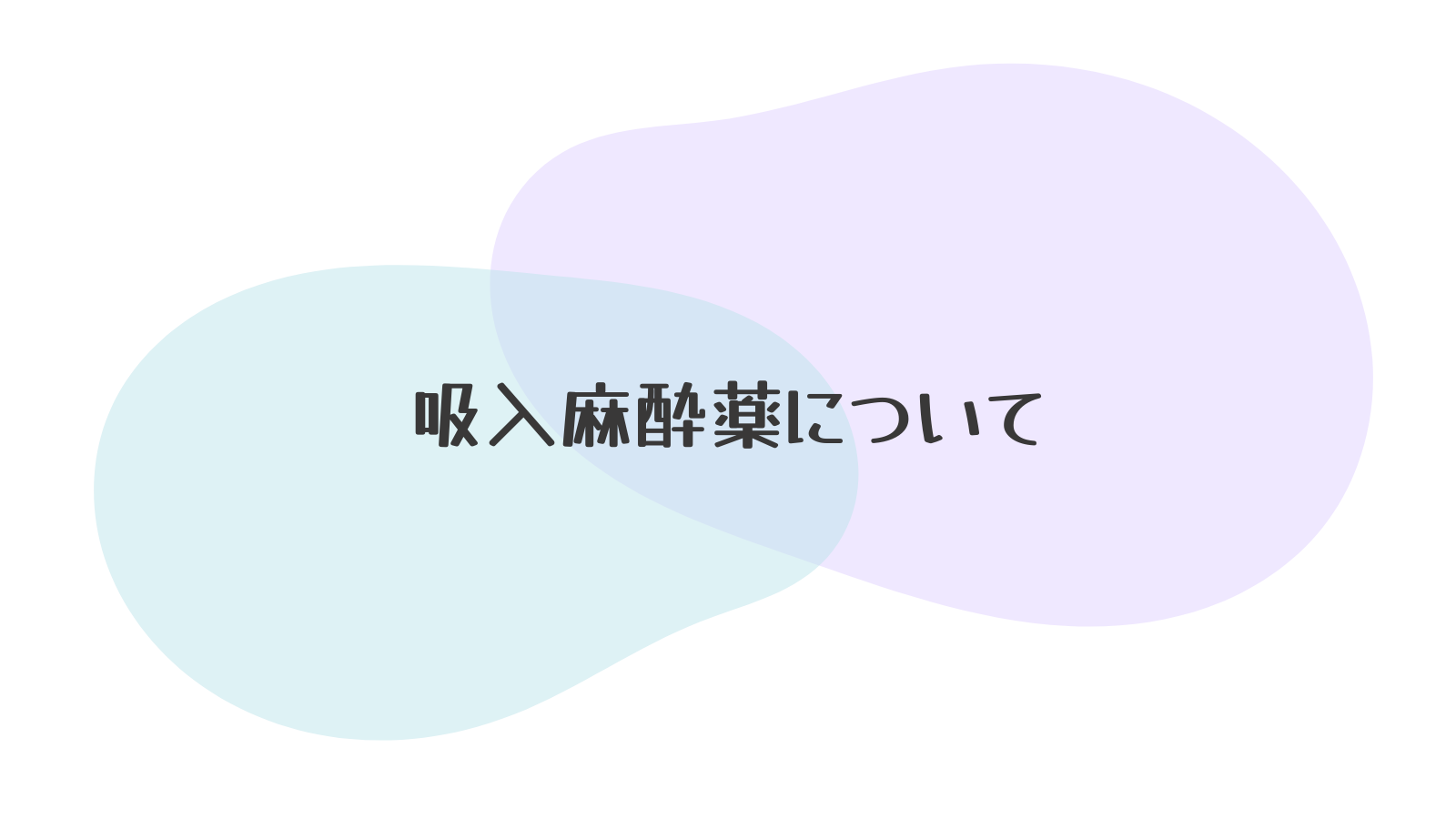
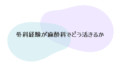

コメント